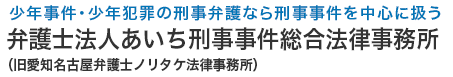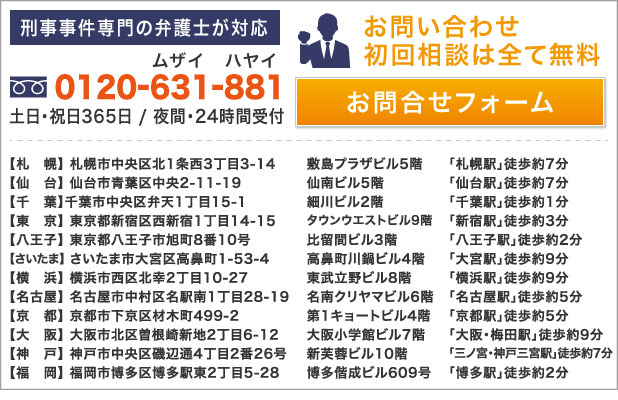釈放・保釈してほしい
1 捜査段階での活動
⑴ はじめに
事件が発生し捜査機関による捜査の結果,犯人を特定した場合,捜査機関は犯人を逮捕・勾留したうえで捜査を継続するケースと,犯人を逮捕・勾留せずに在宅のまま捜査を継続するケースの二つが考えられます。
逮捕・勾留された場合には,勾留延長を含めると最長で23日間身柄が拘束される可能性があります。
少年事件・少年犯罪であっても,一般的な刑事事件と同様に,少年を逮捕・勾留することが考えられます。
そこで,このような長期にわたる勾留を避けるために,以下のような活動を行います。
⑵ 勾留決定阻止
ア 検察官に対する働きかけ
勾留を避けるため,検察官が勾留請求する前に,検察官に対して本件について勾留の要件を満たさない旨を述べて勾留請求をしないように働きかけます。
イ 裁判官に対する働きかけ
検察官が勾留請求した場合には,裁判官に対し勾留請求を却下するよう働きかけます。
⑶ 勾留決定に対する不服申立て
ア 勾留決定に対する準抗告,準抗告棄却に対する特別抗告
勾留が違法・不当であると判断した場合には,勾留に対する準抗告を行い,かかる準抗告を棄却された場合には,最高裁判所に対する特別抗告を行います。
イ 勾留取消請求,勾留の執行停止の申立て
勾留決定後に事情が変わり,勾留が違法・不当となった場合には,勾留取消請求や勾留の執行停止の申立てを行います。
⑷ 勾留延長決定阻止
ア 検察官に対する働きかけ
検察官に対して,勾留延長請求をしないように意見書を提出します。
イ 裁判官に対する働きかけ
検察官が勾留延長請求した場合には,裁判官に対し勾留延長請求を却下するよう働きかけます。
⑸ 勾留延長決定に対する不服申立て
勾留延長決定に対する準抗告や,勾留取消請求などにより,勾留延長を争います。
⑹ 勾留場所を争う活動
少年が勾留されると,警察の留置施設が勾留場所とされることが多いところ,留置施設は,少年の心身に与える悪影響は大きく,長時間の取調べによる自白の強要の危険にさらされ続けることとなります。
そこで,勾留が避けられない場合,勾留場所を鑑別所とするよう働きかけます。
⑺ 接見禁止を争う活動
接見禁止の裁判に対する準抗告や,接見禁止の解除の申立てを行います。
2 家庭裁判所送致から審判までの活動
⑴ はじめに
捜査機関による捜査が終了すると,少年事件・少年犯罪は家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所へ送致された後,家庭裁判所が少年を鑑別所に送るかどうかを判断します。
少年鑑別所に送致されることになると,一般的に4週間程度少年鑑別所で生活することになります(最長で8週間)。
少年鑑別所は刑務所等とは異なり,少年の資質を調査・分析し,少年の改善更生のための適切な処遇方針が検討されることから,少年の更生を考えるうえで,プラスに働く部分もあります。
一方で,少年鑑別所に入ることで,現在通っている学校から退学させられたり,勤務している職場から解雇されたりする危険は高まります。
そこで,付添人として,観護措置を争うか否かについては,少年及び保護者の方に十分に説明したうえで,少年にとっていずれが適切といえるか判断することになります。
仮に観護措置決定を争う場合には,以下のような活動をします。
⑵ 観護措置決定阻止
観護措置の要件・必要性がないことや観護措置を避けるべき事情があることについて述べた意見書を家庭裁判所に提出します。
⑶ 観護措置決定に対する異議申立て・観護措置取消の申請
観護措置決定等が違法・不当であると判断した場合には,観護措置決定等に対し,異議申し立てをします。
観護措置決定後の事情の変化によりその必要がなくなった場合には,観護措置取消の申立てを行います。
3 検察官送致から刑事裁判までの活動
⑴ はじめに
審判において検察官送致決定がなされたときに,その時点で少年鑑別所収容の観護措置が取られている場合,その観護措置は勾留とみなされます(これを「みなし勾留」といいます。)。
みなし勾留の場合,家裁送致前に勾留状が発せられていたのであれば,勾留の延長ができません。
この場合,勾留期間は10日間となります。
⑵ みなし勾留に対する対応
みなし勾留に対しては,通常の勾留と同じく,準抗告,勾留取消し,勾留の執行停止,勾留理由開示の制度が認められていることから,少年の身柄拘束に向けて適時対応していくことになります。
4 公判段階での活動
⑴ はじめに
身柄拘束が続いている少年が起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。
起訴後の裁判段階においても,勾留に対する不服申立て等の手段は存在しますが,釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。
⑵ 保釈について
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈の多くは、弁護人からの請求によってなされ、弁護人が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。