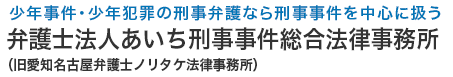少年法一部改正(令和4年4月施行)
※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
1 少年法が適用される年齢
令和4年(2022年)4月1日に,改正少年法が施行されることになりました。
これに先行し,民法の成人年齢が現在(2022年3月31日まで)の20歳から,18歳に引き下げられました。これにより,18歳・19歳の人が,自由に売買などの契約をすることができるようになり,責任ある社会の主体と捉えられることになりました。
今回の少年法改正は,成人年齢の引き下げと論理的には関係があるものではありませんが,18歳・19歳の少年(性別にかかわらず,少年と呼びます)を,17歳以下の少年と区別して取り扱うこととしました。
これから,改正少年法でどのような点が変更されたのかを見ていきます。
最初に,少年法が適用される年齢について説明したいと思います。
以下のような例を基に,これまでとこれからの違いを説明していきます。
〔モデルケース〕
神戸市に住むAさんは,お小遣いが十分にもらえないことや,無駄遣いをしてしまったことから,お金に困っていた。しかし,どうしても欲しい商品があったことから,三宮駅近くの繁華街にある衣料品店でTシャツを1枚盗んでしまった。
Aさんが服をカバンに入れた後,たまたま店の店員に見つかってしまい,店員に腕をつかまれたが,このままでは大変なことになると思ったAさんは,とっさに店員を押し倒し,そのまま走って逃げた。
しかし,数日後,防犯カメラなどの証拠を基に捜査した警察が,Aさんを逮捕しに来た。
まず,事件日も含め,すべて令和4年4月1日以降を前提に考えていきます(そうでない場合は後述)。
このモデルケースは,窃盗犯人が,逮捕を免れるために暴行を加えたので,事後強盗罪(刑法238条)に当たる可能性もありますし,それよりも軽い窃盗罪+暴行罪という組み合わせとなる可能性もあります。事後強盗罪は,5年以上の拘禁刑となる非常に重い罪で,新少年法では原則検察官送致(逆送)事件(新少年法62条2項2号)に該当し,原則成人と同じ裁判を受ける罪です。これに対し,窃盗罪+暴行罪では,原則検察官送致(逆送)事件となりませんから,基本的にはこれまでの少年法と同じ手続きで進んでいきます。
刑事事件の大まかな流れは,改正後の少年法でも変わりがありませんが,少年が罪を犯した場合,①最初に警察などの捜査機関が捜査をし②その後原則的にすべての事件が家庭裁判所に送られ調査等が行われ③調査を踏まえて少年審判が開かれ④場合によっては刑事裁判を受けるという流れで進んでいきます。
少年が対象の場合も①の捜査と④の刑事裁判は刑事訴訟法という法律に基づいて処理されますが,これに少年法が一定の制限を加えています。そして②③はまさに少年法がその手続きを定めています。
これまでの少年法では,事件を起こした時に20歳を超えていたかどうかと家庭裁判所の手続きや少年審判の段階で20歳になっていたかという2つ点から,適用される法律が決まっていました。
それでは,モデルケースを基に,Aさんはどのような法律で審理をされていくのかを見ていきましょう。それには,Aさんが各手続きの段階で何歳であったのかが鍵となってきます。また,一旦は③の段階,つまり少年審判の時点までを考えていきます。③と④の間に18歳を迎えた場合には,そこでも適用される法律が変わってきますが,ここでは③までのことだけを考えていきます。
⑴事件を起こした時に18歳未満であり,少年審判を受けるときも18歳未満の場合
これが最も単純な場合です。この場合には,基本的に改正前の少年法と同様,少年法の規定に従って手続きが進んでいきます。そのため,これまでの少年法の解説などに記載されていることが基本的には当てはまります。
⑵事件を起こしたときは18歳未満だったが,その後18歳を迎え,少年審判を受けるときには18歳・19歳となっていた場合
この場合,家庭裁判所の少年審判を受ける際には「特定少年」という扱いになり,そこでは新しい法律による処理が行われます。たとえば,モデルケースよりももっと軽い罪の場合に,検察官送致が行われる可能性があるなどです(後述)。
しかし,最も影響が大きい原則逆送(検察官送致)事件となるかどうか(新少年法62条2項2号)については「その罪を犯すとき特定少年にかかるもの」が対象ですから,事件を起こしたときに18歳未満であれば,罪を犯すときには特定少年となりませんので,新少年法62条1項2号の適用はありません。ただし,同条1項の適用はありますから,絶対に検察官送致にならないというわけではありません。
⑶事件を起こした時は18歳未満だったが,警察が捜査を終了するまでに20歳を超えてしまった場合
何らかの理由で捜査が遅れ,すぐに捜査が始まらなかったような場合には,このようなことが起きます。
これについてもこれまでの少年法と変わりがありません。つまり,事件捜査が終了し,検察庁が処分をする段階で20歳以上となっていると,事件を家庭裁判所に送ることはできず,成人事件と同様検察官が起訴・不起訴を決定します。また,一旦事件が家庭裁判所に送られた後,少年審判を受けるより前に20歳に到達してしまった場合には,その時点で年齢超過により検察官送致となり,同じく検察官により起訴・不起訴が決定されます。
ただし,この場合でも罪を犯した時に特定少年ではありませんから,資格制限の緩和(少年法60条)や推知報道の禁止(少年法61条)の適用があります。新少年法67条6項や68条の適用はありません。
⑷事件を起こした時は18歳・19歳で,20歳までに全手続きが終了する場合
この場合には,罪を犯した時に18・19歳ですので,特定少年となります。
そのため,モデルケースが事後強盗罪となるとすれば,新少年法62条2項2号の適用があり,原則検察官送致すべき事件として処理されます。
また,20歳までに手続きが終了するため,少年審判を受けることになりますが,少年審判で検察官送致決定を受けると,新少年法67条や68条の適用を受け,資格の取得が制限されたり,実名報道が解禁されたりすることになります。
⑸事件を起こした時は18歳・19歳だったが,途中で20歳を超えてしまった場合
この場合は⑶と同じ流れとなり,検察庁が処分をする段階で20歳以上となっていると,成人同様の起訴・不起訴の決定がなされ,家庭裁判所に移った後20歳となった場合には,その時点で年齢超過による検察官送致がなされます。
ただ,⑶と異なるのは,罪を犯した時に特定少年となっていますので,資格の取得制限や,実名報道の解禁などの特則が適用されます。
これまでは年齢の基準が20歳かどうかだけでしたが,これからは18歳と20歳の2カ所に基準が設けられ,各手続きの段階で何歳かによって適用される条文がことなるという複雑な状況となりました。
2 改正少年法の適用時期
次に,新しい少年法がいつから適用されるかを見ていきます。
ケースは前回と同じケースを用います。
〔モデルケース〕
神戸市に住むAさんは,お小遣いが十分にもらえないことや,無駄遣いをしてしまったことから,お金に困っていた。しかし,どうしても欲しい商品があったことから,三宮駅近くの繁華街にある衣料品店でTシャツを1枚盗んでしまった。
Aさんが服をカバンに入れた後,たまたま店の店員に見つかってしまい,店員に腕をつかまれたが,このままでは大変なことになると思ったAさんは,とっさに店員を押し倒し,そのまま走って逃げた。
しかし,数日後,防犯カメラなどの証拠を基に捜査した警察が,Aさんを逮捕しに来た。
また,Aさんは事件を起こした時にすでに18歳であり,現在もまだ18歳であるものとする。
⑴原則検察官送致(逆送)事件として扱われるかどうか
先ほども見た通り,Aさんの行為は事後強盗罪に当たる可能性があり,そうなると新少年法によると原則検察官送致(逆送)となる事件に該当します。では,いつの事件から新少年法が適用されるのかが問題となりますが,少年法等の一部を改正する法律附則2条は
第一条の規定による改正後の少年法(以下「新少年法」という。)第六十二条及び第六十三条の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致について適用する。
と定めています。
つまり,Aさんの事件が,令和4年4月1日以降に発生したものであれば新少年法が適用されることにより,原則検察官送致(逆送)事件として扱われ,反対に令和4年3月31日より前に発生した事件であれば,そのようには扱われません。ただしモデルにした事後強盗罪などの場合には,改正前の少年法20条1項によって検察官送致(逆送)をされる可能性がありますから,改正前の法律であれば必ず保護処分(少年院送致・保護観察処分等)になるというわけではありません。
⑵人の資格の制限について
改正前少年法60条1項では,
少年のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす
とされ,少年のときに犯した罪で検察官送致(逆送)され,刑事罰を受けたとしても,資格取得の制限(たとえば,医師であれば罰金以上で免許が与えられない場合があるなど)を適用しないこととされていました。
しかし,今回の少年法改正により,少年法60条は,特定少年のときに犯した罪により刑に処せられた者には適用しないこととされました(新少年法67条6項)。
この新少年法67条6項には,少年法等の一部を改正する法律附則6条が
十八歳以上の少年のとき犯した罪により刑に処せられてこの法律の施行前に当該刑の執行を受け終わり若しくは執行の免除を受けた者又は十八歳以上の少年のとき犯した罪について刑に処せられた者でこの法律の施行の際現に当該刑の執行猶予中のものに対する人の資格に関する法令の適用については、新少年法第六十七条第六項の規定は、適用しない。
と定めています。
ですので,令和4年4月1日までに,少年のとき(ここでは20歳未満の意味)に犯した罪を理由に刑に処せられた人については,新少年法67条6項の規定はなく,これまで通り少年法60条が適用され,資格取得の制限は適用されません。
しかし,Aさんの事件が,たとえ令和4年4月1日より前に発生した事件であったとしても,その後の少年審判で検察官送致(逆送)決定を受け,Aさんが令和4年4月1日以降に刑を受けることとなった場合には,「特定少年のときに犯した罪」により刑に処せられることには変わりありませんから,新少年法67条6項の規定が適用され,資格取得が制限されることになります。
⑶推知報道の禁止について
これについても⑵とほとんど同じ状況です。
改正前少年法61条では,少年の事件について少年の個人が特定されるような報道(推知報道)は禁止されていました。
しかし,新少年法68条は
第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。
と定め,略式起訴を経て略式命令が確定したような場合を除き,報道の禁止を除外しました。
そして,少年法等の一部を改正する法律附則7条は
新少年法第六十八条の規定は、この法律の施行後に公訴を提起された場合について適用する。
と定め,令和4年4月1日以降に起訴された事件で,特定少年の時に犯した罪である場合に,推知報道が解禁されることになっています。
Aさんの事件でいうと,たとえ事件発生が令和4年3月31日より前の日であったとしても,令和4年4月1日以降に家庭裁判所で検察官送致(逆送)決定を受け,検察官により起訴をされた場合には,新少年法68条の適用が認められ,Aさんの事件を成人の事件と同様に報道することが許されることになります。
反対に,Aさんが令和4年3月31日より前に検察官に起訴をされ,裁判をしている途中に令和4年4月1日を迎え,まだ判決の言い渡しがなされていないような場合であっても,公訴の提起(起訴)が令和4年4月1日より前の日ということになるので,新少年法68条は適用されず,推知報道は禁止されたままということになります。
3 検察官送致の特則
〔モデルケース〕
姫路市に住むBさん(18歳 高校3年生)は,これまでに女性と交際したことがなく,性的なことに興味を持ったことから,令和4年8月2日,網干駅近くの路上を歩いていた被害者の女性を無理矢理近くの公園内トイレに押し込み,性交を行った。そのとき,被害者には手や足に全治7日程度のかすり傷が生じた。
⑴現在の検察官送致(逆送)事件
少年法が適用され,少年審判を受けると,多くの場合には少年院送致や保護観察といった保護処分を受けることになります。
しかし,一定の重大事件や,道路交通法違反,交通事故といった部類の事件では,少年の教育を主とした保護処分ではなく,成人同様の刑事罰を受けさせることが適当として,事件を再び検察官の手元に戻し,検察官が起訴をした上で,刑事罰を受けることとなることがあります。この,家庭裁判所が事件を検察官に戻す決定のことを,「検察官送致」や「逆送」という名称で呼んでいます。
この検察官送致(逆送)という制度自体は,令和4年3月31日までの少年法にも規定があり,以下のような場合に検察官送致(逆送)されることとなっていました。
第十九条 2 家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
第二十条 家庭裁判所は、死刑、拘禁刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
1つは,少年法19条2項に基づく検察官送致(逆送)で,事件が家庭裁判所に係属した後,20歳となったような場合です。少年審判を開く要件として,対象者が少年(ここでは20歳未満)である必要がありますから,20歳を超えてしまうと少年審判を開けないため,事件を検察官に戻します。
2つ目に,20条1項の検察官送致で,事件の内容等に照らし,保護処分ではなく刑事処分が相当であると思われるときに検察官送致(逆送)をするものです。どのような事件に適用されるかについては特に指定があるわけではないですが,これまでの例では,過失運転致死傷事件(交通事故)や,軽微な交通違反の事件などが検察官送致(逆送)されることが多くなっていました。
3つ目は,その20条1項の例外規定となる20条2項の検察官送致(逆送)です。殺人・傷害致死・強盗殺人・強制性交等致死・保護責任者遺棄致死など,故意の犯罪行為により,人が死亡するに至った事件について,事件が発生したときに少年が16歳以上であった場合には,原則として検察官送致(逆送)することとなっていました。非常に重い事件については,保護処分ではなく刑事処罰の方が国民感情などに沿うと考えられたからです。ただし,保護処分が相当であると認められる事情があった場合には,検察官送致(逆送)せず,保護処分とすることができます。
これら3つの規定は,改正後もそのまま適用されます。新少年法の検察官送致(逆送)規定は,あくまで18歳・19歳の特定少年に対して特則を定めているだけで,14歳から17歳までの少年や,途中で20歳を迎えた者に対しては,これまで通りの規定が適用されることになります
モデルケースのBさんは,強制性交等致傷に当たり,無期拘禁刑か6年以上の拘禁刑に処せられる極めて重い罪を犯しています。成人であれば,裁判員裁判の対象事件です。しかし,改正前の少年法では,少年法20条2項に該当する事件ではなく,あくまでも20条1項により検察官送致(逆送)するかどうかが判断されていました。
⑵罰金以下のみに当たる罪(20条1項の改正)
改正少年法では,特定少年について検察官送致の対象となる事件が拡大されました。新少年法62条1項は
家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第二十条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
少年審判を受ける時点で18歳以上となっている場合(事件日の年齢は関係なく),刑事処分を相当と判断されると,検察官送致(逆送)することができるようになりました。
少年法20条では「死刑,拘禁刑に当たる罪」の場合しか検察官送致(逆送)することができませんでした。そのため,罰金以下の刑しかない罪は,検察官送致(逆送)をすることができないことになっていたのですが,18歳・19歳の特定少年が責任ある主体としての立場を有するようなった改正後は,拘禁刑以上の刑がないというだけで刑事罰の対象から除外することは不適当と考えられ,改正がなされました。
なお,先ほど少し触れたように,実際多くの軽微な道路交通法違反事件では,罰金刑を念頭に検察官送致(逆送)決定が出され,その後検察官が略式起訴等を行い,裁判所で罰金の言渡しを受けることが多くなっていました。このような実情に合わせた面もあります。
⑶原則逆送事件事件の拡大
次に,原則逆送事件が拡大されました。現在の規定では,16歳以上の時に犯した故意の犯罪行為で人が死亡した場合のみが検察官送致(逆送)の対象となっていました。
しかし,新少年法62条2項は
前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)
と定めています。
少年法62条2項が念頭においているのは,少年審判を受ける時点で18歳・19歳の特定少年です。
そして,その特定少年が①16歳以上で故意の犯罪行為により人を死亡させた場合と②特定少年のとき(つまり18・19歳)に死刑・無期拘禁刑・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した場合に原則検察官送致(逆送)をする旨決定しています。
①については,少年法20条2項とそれほど違いがありません。
しかし②が新たに加えられた結果,原則検察官送致(逆送)となる事件が飛躍的に増加しました。具体的には,強盗罪・強盗致傷罪・強制性交等罪・強制性交等致傷罪・現住建造物放火罪などが対象となるようになりました。特に,強盗罪などの場合には,窃盗の機会に追いかけてきた被害者を押したような事後強盗罪も同じ罪の重さであるため,比較的単純な事件でも,少年法62条2項の対象事件となってしまいます。
ここで再びモデルケースに戻ります。 モデルケースのBさんの行為は,既に述べた通り強制性交等致傷となり,無期拘禁刑か6年以上の有期拘禁刑となる事件です。
Bさんは,事件当時18歳の高校3年生ですから,特定少年に該当し,かつ無期拘禁刑が定められた罪を犯していますから,新少年法62条2項2号の対象となり,原則検察官送致(逆送)事件となります。これまでであれば保護処分となっていた可能性のある事件でも,これからは検察官送致(逆送)となり,刑事処分を受ける可能性が高まるということができます。
⑷少年法55条の扱い
事件が検察官送致(逆送)され,検察官により起訴がなされると,刑事裁判が開かれます。しかし,この刑事裁判の中で,やはり刑事処罰より保護処分の方が適当であると判断される場合があります。このときは,少年法55条により
裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
とされていることから,再び事件が家庭裁判所に戻されることになります。そして,基本的には戻された家庭裁判所では保護処分が言い渡されることになります(決まりはないので,もう一度検察官送致(逆送)になるケースもあります)。
この少年法55条については,今回の改正では一切の変更が加えられていません。
そのため,特定少年が検察官送致(逆送)決定をされ,刑事裁判を受けることになった場合であっても,少年法55条に基づき,家庭裁判所に移送される可能性はあります。
Bさんの事件で,検察官送致(逆送)決定を受けた場合であっても,刑事裁判で少年法55条の決定を受けた場合には,再び事件が家庭裁判所に戻され,多くの場合には保護処分を受けることになると思われます。
4 保護処分の特則
次は,保護処分の特則です。原則検察官送致(逆送)事件は,比較的重い罪を対象としていましたが,この特則は特定少年の事件すべてに適用されます。
新少年法64条1項は,以下のように定めています。
第二十四条第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、第二十三条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなければならない。ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、第一号の保護処分に限り、これをすることができる。
一 六月の保護観察所の保護観察に付すること。
二 二年の保護観察所の保護観察に付すること。
三 少年院に送致すること。
少年法24条1項は,少年に保護処分を課す際に,保護観察・少年院送致等の処分ができることを規定するものです。しかし,少年法24条1項は,少年がどれだけ更正・教育する必要性があるのかという,要保護性の程度に応じて処分を課すものとなっています。そのため,極端な例でいうと,10円のガム1つを万引きした初犯の少年を,少年院送致することも可能です(成人であれば,おそらく起訴猶予となる可能性が高いです)。
しかし,民法上成人となり,親の監護から外れる18歳・19歳に対し,要保護性を理由に,犯した罪の重さと不均衡な処分を行うことは,責任主義などの要請との関係で許されないと考えられたことから,特定少年に保護処分をする際には,犯した罪の重さを考慮して,「相当な限度を超えない範囲内」という上限を定めることとなりました。
保護観察期間として規定されている6か月,2年という長さは,従前の保護処分の内容と変わりません(18歳の少年が保護観察を受けるときは,その期間は20歳までではなく,原則2年でした)。
また,少年院送致となる期間としてもは,これまで原則は20歳まで,最長で23歳になるまでとされていましたが,新たに審判の際に少年院に収容する期間として 3年以内の期間を定めることとなりました(新少年法64条3項)。
5 ぐ犯の不適用
⑴ぐ犯とは
少年法は,「少年の健全な育成を期し,非行ある少年に対して性格の矯正及び環境の調整」を行うものです。
そのため,現に罪を犯した少年だけではなく,罪を犯す可能性があるような少年に対しても,処分の対象としてきました。この「罪を犯す可能性がある」ことを「ぐ犯」と呼んでいます。
ぐ犯に該当する事由は,少年法3条1項3号に列挙されており
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
このような事情がある場合には,ぐ犯事件として,実際に罪を犯したのと同じように家庭裁判所で少年審判を受けることとなります。
たとえば,深夜徘徊を繰り返して家に戻らなかったり(イ・ロ),暴力団など反社会的勢力と言われる人と交友関係を持ち,行動を共にしていた場合(ハ)がこれに当たるほか,最初は何らかの犯罪があったとして警察が捜査をしたものの,厳密な事実認定をすることができず,疑わしいような状況だけが残った場合にぐ犯として家庭裁判所に送られることが多くなっています。
⑵ぐ犯の不適用
これに対し,新少年65条1項は
第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、特定少年については、適用しない。
と規定し,特定少年についてはぐ犯の規定を適用しないことが定められています。
つまり,18歳・19歳の少年が,ぐ犯を理由に家庭裁判所で保護処分を受けることはないということです(ぐ犯の事由は,それ自体はいずれも犯罪ではないので,検察官送致をされたり,刑事処分を受けたりすることもありません)。
これも,民法上成人として扱われる特定少年に対して,監護を前提とするようなぐ犯での処分をすることが妥当ではないと考えられたからです。
なお,18歳になる前にぐ犯として家庭裁判所に送られた後でも,審判を受ける前に18歳に到達すれば,ぐ犯として少年審判を受けることはありません。
6 刑事事件の特則
少年が事件について捜査を受けるときは,基本的には刑事訴訟法に基づいて手続きが進みますが,これに対して少年法が例外を設けています。
たとえば,
・少年を勾留する場合には「やむを得ない場合」でなければならない(43条3項,48条1項)
・少年を留置する場合には他の被疑者・被告人(成人)と分離しなければなない(49条1・3項)
・少年の刑事事件と他の共犯者の事件は基本的に分離して裁判しなければならない(49条2項)
・少年に有期の拘禁刑の実刑判決を言い渡すときは,不定期刑(●年から●年というように,刑の重さを1点に決めないこと)を言い渡すことや,その場合でも上限は15年以下,下限は10年以下とすること(52条)
といった例外が定められています。
改正少年法67条により,これらの規定に変更が加えられました。
検察官送致(逆送)決定を受けた後の特定少年は,「やむを得ない場合」でなくとも,成人と同じ条件で勾留することとなり,他の成人との分離も必要なくなります(新少年法67条1・2項)。
また,特定少年の刑事裁判については,少年であるからという理由での分離は行われず(新少年法67条3項),実刑判決を言い渡す際にも,不定刑ではなく,成人と同様「拘禁刑●年」というような形で刑の重さが1点で決まるようになります(新少年法67条4項)。また,刑の重さの上限などもなくなり,成人同様法定刑の範囲で処断されることになります(同)。
7 資格の取得・推知報道の特則
〔モデルケース〕
豊岡市に住むCさんは,国道178号線沿いの飲食店を放火したとして現住建造物等放火(法定刑:死刑又は無期若しくは5年以上の有期拘禁刑)で逮捕され,家庭裁判所で検察官送致決定を受けました。そしてすぐに検察官により起訴され,この後裁判を受ける予定です。
Cさんは将来国家資格を取りたいと考えており,その資格は拘禁刑を受けた場合には取得できないこととされています。また,今後報道されると将来就職できなくなるかと心配しています。
⑴資格取得の制限について
少年の更正のため,少年法60条1項は,少年の時に犯した罪に関して特則を設けています。
少年のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす。
たとえば,医師であれば医師法4条3号により,「罰金以上の刑に処せられた者」は医師免許を与えないことがある旨定められています(罰金以上の刑になると,一生医師免許を与えられないというわけではなく,罰金の場合には5年経過するとこの規定が適用されなくなります(刑法34条の2))。また,弁護士であれば弁護士法7条1号により「拘禁刑以上の刑に処せられた者」は弁護士となる資格を有しない(拘禁刑の場合には10年経過すると規定の適用が無くなります)こととされています。
このように,罰金以上の刑を受けると,5年か10年の期間,資格の取得が制限されることになります。
少年法60条1項の定めは,少年が刑事処分を受けた場合に,このような資格取得の制限を撤廃するものとなります。ですので,国家試験に合格しほかの欠格事由がなければ,罰金刑を受けてから5年以内であっても医師になることができます。
ただし,これはあくまで「人の資格に関する法令の適用について」のみの話ですから,前科がなかったことになるようなものではありません。
そして,今回の新少年法67条6項は
第六十条の規定は、特定少年のとき犯した罪により刑に処せられた者については、適用しない。
と定め,特定少年の時に犯した罪により刑に処せられた場合には,資格取得の制限の緩和が適用されないことを規定しています。
なお,あくまで「特定少年の時に犯した罪」で刑に処せられる場合ですから,たとえば17歳の時に強盗事件を起こし,その後検察官送致(逆送)決定を受けた後,18歳で拘禁刑を受けたような場合には,新少年法67条6項の適用はありません。つまり,この場合には元の少年法60条が適用されますから,資格取得の制限は緩和されることになります。
Cさんの例でいうと,Cさんが17歳のときに放火をし,その後刑事裁判を受けるというような場合には資格取得の制限がありませんから,放火の罪で受けた拘禁刑は考えずに資格を取ることができますが,18歳の時に放火をしたのであれば,刑の執行が終了してから10年の間は,資格を取ることができなくなります。
⑵推知報道の禁止の例外
少年の更正,保護のため,新少年法61条では
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
というように,報道から事件を起こした少年がどこの誰であるかということを推測できるような報道(推知報道)を禁止しています。
しかし,18歳・19歳の特定少年が起こした事件は,責任ある主体が起こした事件であるにもかかわらず,一律に報道を禁止することは適当でないと考えられ,新少年法68条で
第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。
と推知報道禁止の例外が定められました。
これは,特定少年のときに犯した罪により,起訴された場合に,推知報道が禁止されなくなることを意味し,実名報道がなされるようになるという意味です。
ただ,あくまでも「公訴を提起された場合」に限りますから,逮捕され,捜査されているときや,少年審判を受けているときなどは,たとえ特定少年であったとしても,推知報道は禁止されています。
また,同条但書記載の通り,略式起訴されたような事件で,正式裁判が開かれなかったような事件については,事件が比較的軽微であることや,少年の更正・社会復帰を支援する観点から,なお推知報道が禁止されています。
そして,⑴と同じことになりますが,特定少年のときに犯した罪により公訴を提起される場合に限られますから,17歳の時に強盗事件を起こし,その後18歳になって起訴されたような場合では,特定少年の時に罪を犯したわけではないので,今まで通り推知報道は禁止されることなります。
なお,この報道について最高検察庁が通知を出しており,実名公表を検討すべき事案としては「犯罪が重大で,地域社会に与える影響も深刻な事案」であり,具体的には裁判員対象事件(殺人,放火,強盗致死傷,強制性交等致死傷)となることが挙げられています。
Cさんの例でいうと,この事件は裁判員裁判対象事件となりますので,Cさんが18歳になってから放火をしていたのであれば,実名での報道がなされる可能性が高いことになります。反対に,Cさんが17歳の時に放火をし,その後刑事裁判を受けるという場合には,同じく裁判員裁判になりますが,推知報道は禁止されるので,実名報道はなされません。
8 付添人選任権者の拡大
改正前の少年法10条では,少年と保護者しか「付添人」を選任することができませんでした。
「付添人」とは,典型的には弁護士ですが,少年の利益を擁護し,適正な審判・処遇決定のために家庭裁判所で活動をする者を指します。
従来は20歳未満は親権に服していたので,保護者が存在しましたが,民法上成人が18歳となったので,18歳・19歳の少年には保護者が存在しないこととなりました。
そこで,新少年法10条では「少年並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹」が付添人を選任できるようになりました。