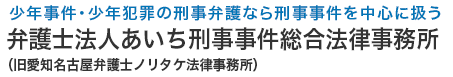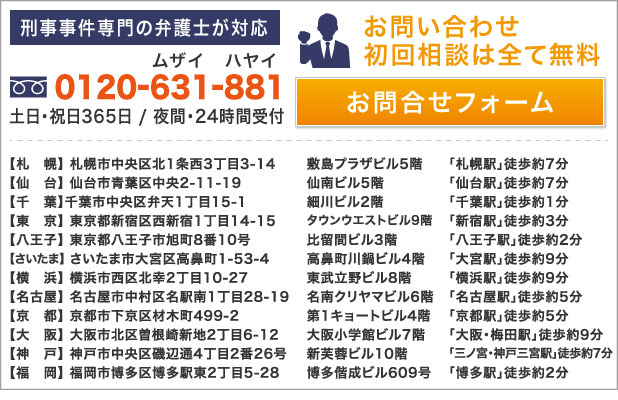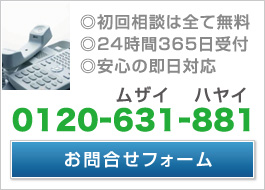執行猶予にしてほしい
※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
1 執行猶予とは
刑事事件における執行猶予とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずに済めば、刑務所で服役せずに済む制度です。
例えば,「拘禁刑1年執行猶予3年」という判決の場合、3年間の執行猶予期間に一度も罪を犯さなければ、刑務所に行かなくてもよいことになります。
ただし,3年間の執行猶予期間に再度罪を犯せば、執行猶予は取り消されることがあります。
この場合、前の判決の1年間と新たに言い渡された刑を合算させた期間、刑務所に行くことになります。
執行猶予判決であれば,刑務所に入らずに普段の生活を送ることができます。
執行猶予を取り消されることなく猶予期間が経過した場合、刑の言渡しは効力を失います。
したがって、資格制限については将来に向けてなくなることになります。
もっとも、将来に向けてなくなるだけなので、執行猶予付き刑の言渡しにより失った資格が当然に復活するわけではありません。
また,刑の言渡しの事実そのものがなくなるわけではないので、その後に同種の犯罪を再び行った場合などは特に情状が重くなり、量刑に影響することが考えられます。
執行猶予の要件
刑事事件における執行猶予には,⑴初度の執行猶予と,⑵再度の執行猶予の2種類があり(そのほかに一部執行猶予という制度もあります),それぞれ要件が異なります。
(1)初度の執行猶予
- 前に拘禁以上の刑を科されたことがないか,執行終了後又は執行の免除を得た日から5年内に拘禁以上の刑に処されたことがないこと
- 今回言い渡された刑が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金であること
- 情状
(2)再度の執行猶予
執行猶予期間中に罪を犯した場合、一般的には実刑判決になると言われています。
しかし、例外的に再度の執行猶予を付される場合があります。
法律上、
- 2年以下の拘禁刑の言い渡しを受け
- 情状に特に酌量すべきものがある
- 再度の執行猶予期間中における犯行ではない(保護観察の仮解除中を除く)
という3点を満たす場合、執行猶予期間中に犯した罪について再度の執行猶予判決を得ることが可能となります。
執行猶予制度の改正
改正刑法に基づき、2025年6月1日から、新しい執行猶予制度が施行されています。2025年6月1日以降の事件に適用される新しい執行猶予制度の主な改正点は以下のとおりとなります。
(1)再度の執行猶予の条件緩和
これまでは、1年以下の懲役又は禁錮刑を言い渡す場合のみ、再度の執行猶予を付すことが可能でした。
改正後は、2年以下の拘禁刑(懲役と禁錮の一本化)を言い渡す場合に再度の執行猶予を付すことが可能になります。
拘禁刑の上限が1年から2年に引き上げられたため、再度の執行猶予の対象となる刑の幅が広がります。
(2)保護観察付執行猶予中の場合の再度の執行猶予
改正前は、保護観察付の執行猶予期間中に再犯した場合、再度の執行猶予を付すことは不可能でした。
改正後は、保護観察付の執行猶予期間中に再犯した場合でも、再度の執行猶予を付すことが可能となります。
ただし、再度の執行猶予期間中に再犯した場合には、保護観察の仮解除中を除き、さらに再度の執行猶予を付すことはできません。
(3)執行猶予期間満了後の再犯の場合の効力継続
執行猶予期間中の再犯について公訴が提起された場合、執行猶予期間満了後も一定の期間は、刑の言渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言渡しが継続しているものとみなされます。
これにより、いわゆる「弁当切り」(前刑を失効させるために公判の引き延ばしをする行為)はできなくなったと考えられます。
執行猶予判決をとるための弁護活動
執行猶予を獲得するためには、裁判において、以下のような被告人に有利な事情を主張・立証することが大切です。
ア 犯罪に関すること
- 犯行態様が悪質ではない
- 計画性がなく突発的な事件である
- 被害が軽微
- 共犯事件での立場が従属的(共犯者に逆らえない、ついて行っただけなど)
- 組織性がない
イ 情状に関すること
- 示談が成立している、被害者が許すという宥恕の意思を表している
- 被害者に謝罪し反省している
- 更生の意志と具体的な再発防止策がある
- 実刑判決になったら家族等周囲の者に重大な悪影響がある
- 前科・前歴がない
- 常習性や再犯可能性がない
執行猶予の取消し
もっとも,執行猶予判決を得てもこれが取り消されることがあります。
⑴ 必要的取消
以下の事由がある場合には,執行猶予が必ず取り消されます。
- 猶予期間中に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、これについて執行猶予の言渡しがないとき。
- 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
- 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
⑵ 裁量的取消
さらに、次の場合にも刑の執行猶予の言渡しが取り消されることがあります。
- 猶予期間中にさらに罪を犯し、罰金に処せられたとき。
- 「保護観察」に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せずその情状が重いとき。
- 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。